【業種別会計】建設業におけるJV(ジョイントベンチャー)は連結対象? JVの位置づけと連結実務を解説
2025年7月3日更新
上浦会計事務所
公認会計士・税理士 上浦 遼
の位置づけと連結範囲に含まれない理由-300x218.png)
1.はじめに
建設業において他社との連携によって事業を推進する手法としてJV(ジョイントベンチャー)が活用されるケースがあります。JVは高難度の大型案件で利用されることが多く、構成員がそれぞれ一定割合を出資する形で運営されます。このJVは法人格は無いものの、組織体として組合に該当するものと解されています。
それでは、JVはその比率によって連結会計の対象とならないのでしょうか。
本稿では、会計上の連結範囲の考え方、そしてJVが連結対象になるか否かについて解説したいと思います。
2.JV(ジョイントベンチャー)とは
(1)JVの概要
JVとは、複数の企業が資金・技術・人材などを持ち寄って、特定の事業やプロジェクトを共同で遂行するための枠組みです。特に大規模で期間限定のプロジェクト、例えば公共工事などにおいて、建設会社同士で結成されることがあります。
(2)建設業界におけるJV特徴
建設業におけるJVは、主に特定の工事の受注・施工を目的として設立されます。
これらのJVは法人格を持たず、構成員企業の一部門や仮想の組織体として存在します。法律上の明記はないものの、民法上の組合であると考えられています。
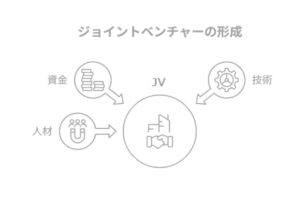
3.連結範囲
(1)連結財務諸表の目的
連結財務諸表とは、親会社とその子会社の財務情報を一体として表示するもので、企業グループ全体の財政状態・経営成績を示すために作成されます。これにより、投資家や債権者などのステークホルダーに対して、経済的実態を開示する役割を果たします。
(2)連結の範囲の判断基準
連結対象とするか否かは議決権比率を始めとした事象から対象の企業を支配しているかどうかで判断します。この判定基準は単純に議決権の過半数を持っているか否かだけではなく、様々な要素を加味する必要があるのですがこの辺りの詳細については本解説の趣旨と異なるため省略します。
本稿において連結範囲の判断基準で重要なのは、連結範囲の対象となるのが株式会社だけではないという点です。
適用指針において、子会社、及び関連会社の範囲に含まれる「会社に準ずる事業体」には、パートナーシップその他これらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が該当するとされており、民法上の組合も対象には含まれています。
4.JVは連結範囲に含まれるか否か
(1)建設業JVの法的性格
前述の通り、日本の建設業界においてJVは、法的には民法上の組合にあたるものと考えられています。
この組織形態に着目すれば連結範囲検討対象に含まれると考えられますが、連結実務上「別個の組織体として認識しないのが適切」と記載があることから、連結範囲には含めていない企業が多いものと思われます。
(2)連結範囲に含まれない理由
連結範囲に含まれない理由として、基準上以下のように記載がされています。
要約すると、JVでは一般的に一定の会計期間で決算を行っておらず、JVが行った取引は構成員がその出資比率に応じて取り込む形が一般的(既に会計情報は取り込んでいる)ので、連結は行わないということとなります。
【連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点 についてのQ&A】(Q12)
| 現行会計実務上は毎年一定の時期に規則的な決算を行うことなく、構成員各社の会計に組み込む形態となっているため、連結実務上では個別の組織体として認識しないことが適切と考えられます。 | ||
5.終わりに
建設業において大規模工事や高難度の工事でJVを利用するケースがあります。
法的根拠が明確でない部分もあるものの、JVも組織であることに違いなく、連結検討対象となるように感じますが、実務上の取扱いへの配慮もあり連結範囲には含まれないのが一般的であるというのが結論となります。
本稿がJVの連結に関する理解の一助になれば幸いです。
当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。
弊事務所では、企業会計(財務会計)に関する支援業務を幅広く提供しております。
初回ご相談時に報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。


