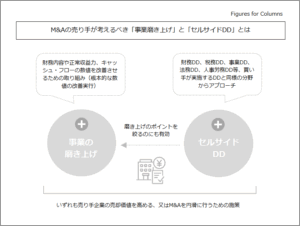M&A実行前に考えるべき「事業の磨き上げ」と「セルサイドDD」 企業価値、事業価値と売買価格の最大化
2025年11月4日更新
上浦会計事務所
公認会計士・税理士 上浦 遼
1.はじめに
昨今、M&Aによる事業承継が注目されて久しいですが、売り手の経営者にとって、M&Aは単なる「会社売却」ではなく、これまで培ってきた想いや信頼を次世代へと引き継ぐ重要な経営判断です。
しかし、多くの経営者にとってM&Aは初めての経験であり、「何から始めればよいのか分からない」という不安を抱えるのは自然なことです。とりわけ、売り手としてM&Aに臨むことは人生で一度きりというケースが大半であり、経験がないがゆえに企業の本来の価値が正しく評価されず、意図しない条件での交渉が進む可能性もあります。
M&Aでは、通常は買い手が専門家を通じてデューデリジェンス(DD)を実施し、対象会社の状況を詳細に調査しますが、売り手側が主体的に実施するセルサイド・デューデリジェンスにも大きな意義があります。自社の財務・法務・労務状況を事前に把握・整備しておくことで、リスクへの対処や企業価値の適切な説明が可能となり、交渉を公正かつ円滑に進めるうえでの基盤が整います。
こうした準備を怠ることで、本来評価されるべき価値が見過ごされてしまうことも少なくありません。M&Aを単なる出口戦略としてではなく、事業の将来を真剣に考える一つの選択肢として前向きにとらえるためには、売り手としての主体的な準備が極めて重要です。
本コラムでは、M&Aにおける「事業の磨き上げ」と「セルサイド・デューデリジェンス(DD)」という二つの視点から、事業価値を最大化するための具体的な準備方法について解説します。
2.事業の磨き上げとは
売り手における「事業の磨き上げ」とは、M&Aに先立って企業内部の状況を整理・整備し、買い手から見た企業の魅力と信頼性を高めるためのプロセスです。これは表面上の決算数値を整えるという意味ではなく、企業の実態と持続可能性を明確に示すことが求められます。
この準備が不十分である場合、企業価値を正当に伝えることができず、価格交渉においてアピールポイントが伝わらない可能性があります。
(1)財務面の整備
①会社の決算情報の客観的評価
M&Aにおいては、過去の決算情報をもとに企業価値が評価されるのが一般的であり、通常は過去3年から5年分の決算書が買い手の評価対象となります。そのため、各会計数値の推移について把握し、説明可能性を高めておくことが重要です。
特に、一過性の収益や費用、例外的な取引などが決算に含まれている場合には、それらを正確に把握し、調整後の実態ベースの利益や安定的な収益力を示せるようにしておくのが良いでしょう。
これにより、企業価値が不当に低く見積もられるリスクを避け、公平な価格交渉が可能になります。
②キャッシュ・フローの可視化と改善
M&Aにおいては買い手企業の方針により、買収価格の算定方法にかなり幅がありますが、買い手企業の規模が大きくなればフリー・キャッシュ・フローやEBITDA等をベースに企業価値を評価するケースがあります。
そのため、自社のキャッシュ・フローを始めとした経営指標を正確に把握し、必要に応じて改善策を講じることが重要です。
売上高や各段階利益(営業利益や経常利益、当期純利益)だけではなく、実際にどれだけキャッシュや付加価値を生み出しているかを明確にすることで、企業の実力を正しく伝えることができます。これらの数値の改善は企業価値の向上に直結する可能性があるのです。
一方、節税対策などの目的で過度な支出を計上している場合には、利益やキャッシュ・フローを圧迫している可能性があり、結果として企業価値の低下に繋がるケースがあります。企業の状況を踏まえ、適宜見直しをする必要があります。
(2)法務・労務の整備
①重要契約書の把握、COC条項の調査
M&Aを進めるにあたっては、事業上の重要な契約を事前に洗い出しておくことが必要です。具体的には、主要な顧客や仕入先、外注先との基本契約、販売代理店契約、業務委託契約、さらには株主間契約などが該当します。
これらの契約書の中には、会社の支配権に変更が生じた際に契約の解除や通知義務が発生するチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が含まれていることがあります。これら基本契約など契約締結時点ではオーナーチェンジなどを想定していないケースも多く、会社側としてもその存在を失念ないしは気付いていないといったことも珍しくありません。
特に、契約書が取引先側で準備されたひな型であった場合、先方の契約ポリシーに基づいてCOC条項が自動的に含まれているケースもあります。こうした条項があると、M&A取引の実行にあたり取引先に通知をしなければならず、場合によってはM&A後に契約が終了、取引条件の見直しを求められたりするリスクが生じるため、内容を確認しておくことが重要です。
②雇用条件の把握、未払残業代の調査
労務リスクは、買い手が最も慎重になる分野の一つです。雇用契約や就業規則、賃金体系、労働時間管理の状況を確認し、未払残業代や社会保険の未加入といった潜在的な問題がないかを検証することが求められます。
また、M&A契約では表明保証条項において未払賃金(給与)が存在しないことを明記することは多く、後々になって未払残業代が発覚した場合、買い手から補償を求められることもあります。そのため、売却前に労務内容を精査し、必要な是正措置を講じておくことは、リスク管理の観点からも極めて重要です。
(3)経営管理体制の見直し
①経営者依存の脱却と組織化
中小企業では、経営者自身の判断や人脈、スキルに強く依存した運営が行われていることが少なくありません。
しかし、M&A後には経営者の継続関与が行われない、ないしは関与の程度が大きく低下するケースは多く、買い手にとっては経営者不在でも事業が持続するかどうかは重要な関心事となります。
そのため、幹部人材の育成や権限の適切な委譲、社内の意思決定フローの見直しといった組織面での整備が求められます。あわせて、業務マニュアルを整備し、ノウハウや業務手順を形式知化することで、事業の属人性を低下させ、買い手にとって安心感のある組織体制を示すことも有効です。
②中期経営計画の策定
買い手にとっては、過去の実績だけでなく、M&A後の将来像も非常に重要な関心事項です。
そのため、成長性や持続可能性を示す中期経営計画を策定し、将来の収益見通しや事業戦略を数値化して提示することは非常に有効であるといえます。
企業価値の算定にあたっては、過去の実績に基づいて評価する方法に加え、将来のキャッシュ・フロー予測をベースにした手法が用いられることもあります。買い手にとって納得感のある計画を提示することができれば、将来の期待を織り込んだ適正な評価につながる可能性があります。
3.セルサイド・デューデリジェンスの実務
セルサイド・デューデリジェンス(DD)とは、売り手側が主体となって自社の財務、税務、法務などの状態を専門家とともに精査し、買い手からの調査に備えるための事前準備です。
(1)セルサイドDDの目的と効果
①買い手の懸念点を先回りで対処
買い手による調査で初めて問題点が発覚すると、条件変更や交渉の長期化、最悪の場合は取引そのものが中止されるリスクもあります。これを防ぐためには、売り手側が主体的に課題を洗い出し、可能な範囲で解決や是正をしておくことが有効です。
交渉に入る時点で未解決の課題が多い企業と、すでに課題が整理され、対応が完了している企業とでは、買い手が受ける印象にも大きな差が出ます。事前に対応しておくことで、信頼性のある企業として交渉に臨むことが可能となります。これは価格交渉においても、問題点が未解決のままであるよりも、あらかじめリスクを洗い出し、対策を講じている状態のほうが、買い手の印象は変わります。
課題に事前に対処いており、減額要因を抑えることができ、結果として納得感のある条件を提示しやすくなります。
②交渉力・信頼性の向上
セルサイドDDを通じて整理された情報を提示することは、買い手との交渉において大きな意味を持ちます。
要求された資料が整っており、論点が事前に把握されている状態であれば、交渉において的確に対応することができ、信頼性のある売り手として評価されやすくなります。
M&Aの交渉を進めるうえで重要となるポイントや論点を、売り手自身が事前に把握しておくことができる点は、セルサイドDDを実施する大きなメリットであるといえます。
(2)実施プロセスと必要資料
①資料準備の必要性と範囲
セルサイドDDでは、会計(決算書、資金繰り表)、税務(法人税申告書、消費税申告書)、法務(定款、契約書、登記簿謄本)、労務(就業規則、雇用契約書)といった多岐にわたる資料について、事前に準備をしておく必要があります。
これらの資料は、いずれにせよ買い手がデューデリジェンスを実施する際に高い確率で提出を求められるものであり、直前になって対応するよりも、あらかじめ整理しておくことで、調査プロセスを円滑に進めることができます。
また、資料が迅速に整備されていることで、買い手に対して信頼感を与えることにもつながります。
②スケジュールと進め方
いつ実施すべきか決まったタイミングはありませんが、M&Aの検討を始めた初期段階でセルサイドDDに着手し、調査範囲を明確にした上で、概ね三か月程度の期間をかけて段階的に進めていくことをお勧めします。
社内のリソースや外部専門家との連携状況を踏まえ、優先順位を定めたうえで計画を立案します。
4.専門家によるM&A支援の意義
M&Aは、財務、法務、税務、労務といった複数の分野にわたる知識と経験を要する、極めて専門的なプロセスです。とりわけ中小企業の経営者にとっては、M&Aは一生に一度あるかないかの大きな意思決定であり、現実的には自力で適切に進めるのは非常に難しい側面があります。
(1)自力対応の限界とそのリスク
①自力でデューデリジェンスを実行する難度
M&Aにおける売却活動は、未経験の状態で実施するには想像以上に高度で煩雑です。
財務、税務、事業、法務、人事労務など各分野いずれにおいても専門的な知識が求められ、社内リソースだけで対応が困難であることは多く、むしろセルサイドDDを社内だけで完結させられる企業は多くないでしょう。
②不十分な対応がもたらす反動
仮に準備や対応が不十分なまま進めてしまった場合、企業価値が適切に評価されない、買い手との信頼関係が築けない、あるいは契約後に想定外の補償義務が発生するなど、後々重大な不利益を被る可能性もあります。M&Aにおいては、正しい準備と判断の有無が結果を大きく左右するため、慎重な対応が不可欠です。
(2)専門家による支援のメリット
①実務支援とアドバイス
専門家の支援を受けることで、事業の磨き上げやセルサイドDDの実行支援、買い手との交渉資料の作成、契約書の内容確認など、各フェーズにおいて適切な対応が可能となります。実務経験のある専門家であれば、過去の成功例や失敗事例をもとに、売り手にとって最適な選択肢を提示可能です。
②精度と安心感の向上
はじめてのM&Aであっても、経験豊富な専門家の助言を受けることで、売り手としての判断や行動に確信を持つことができます。また、専門家の存在が買い手にとっても安心材料となり、信頼性の高い交渉を実現するうえでプラスに作用します。
5.終わりに
M&Aは、会社を手放すことではなく、次の世代へ想いと価値を託すための経営戦略です。その成功には、売り手自身がどのように見られているのかという買い手視点を理解し、その上で自社の魅力と強みを適切に伝える準備が欠かせません。
事業の磨き上げやセルサイドDDは、そうした準備を体系的に進めるうえで有効な手段です。
M&Aを前向きにとらえ、納得のいく結果を得るために、ぜひ早めの段階から取り組んでいただくことをおすすめします。
当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。
弊事務所では、デューデリジェンスを始めとしたM&Aに関する支援業務を幅広く提供しております。
初回ご相談時に報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。